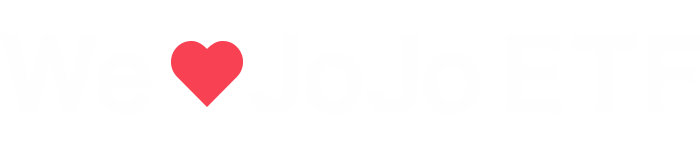- 2025年9月4日
vol.63 資産形成との向き合いかたと出口戦略を考える
老後に向けてどう資産形成をするか
二つの原則があります。一つは、個々人の寿命はわからないので、平均的な寿命を想定せざる得ないことです。
もう一つは、できれば死ぬ時には資産がちょうどなくなるのが幸せだろうということです。子や孫に資産を残そうとする人はそれ以外の部分については同じことになります。
平均的な寿命に合わせてうまく資産形成ができても、長生きリスクがあり(お金が足りなくなる)、一方で運悪く短命であれば資産を残すことになります。資産を残すことはそれほど不都合ではありませんが、わかっていたらもっと使ったのに、ということにはなるでしょう。引退時に3,000万円必要などという言説もありましたが(実際は平均的にそのくらいの人が多いという程度の話で必要という意味ではなく、多分そんなになくても大丈夫に思いますが)、生き方によって金額は違うし、個性があることを忘れてはいけません。人と同じという考えより、自分はどうなるとまあ満足できるだろうか、を考える必要があります。これは、誰かに教えてもらうことはできません。お金で買えるものが好きな人もいればそうでもない人もいます。さらに難しいのは人は考えを変えるということです。ある時期まではこうだったが今となってはこう思うということも多いですよね。
自分の寿命が分からない中で、金融資産を使い切れない、あるいは足りなくなる状況を避けるためにはどうしたらいいのかを考える必要がありますが、実際には答えが明確に一つ決まるわけではありません。誰にでも通用する出口戦略があるともいえないでしょう。

出口戦略の代表的なパターンを知っておく
そもそも投資の出口とはなんでしょうか。年齢は人によりますが、引退する時を老後のスタートだとすると、まず多くの場合収入が非常に低下します。会社員だった人は厚生年金がスタートするかもしれません(これも色々選択できますが)。フリーランスの人では国民年金があるはず(しばしば入っていないという人もいますが)ですが、厚生年金より少ないことが多いので、自分で貯めている(あるいは投資している)はずと想定されます。この辺りのスタートラインから人により様々です。ここでは投資の出口戦略ですから、サラリーマンであれフリーランスであれ、引退することにしてこれまで多少は積立投資をしてきたとしましょう。その出口をどう考えるかです。
引退とは投資で言えば取り崩しのスタートです。これまで成長投資として世界株式などに積み上げ、配当も再投資していたでしょう(そう祈ります)。それを取り崩しに回していきましょう。取り崩しを自分で売却しながら行っていくことはもちろんできます。取り崩ししなかったお金はそのまま成長投資に向かっていることになります。
しかし、私の好みは、引退後は毎月分配や年金が出ない月に払われる隔月分配のETFや投資信託に乗り換えることです。一気に進める必要はないですが、できるだけ早めに月々の収入の上積みを想定できるように切り替えるのです。毎月分配や隔月分配はそれがしやすいように高配当株式やリート(不動産投資信託)に依拠した投資が多く、投資全体を成長から分配にシフトしていく効果があります。しかも、株式主体のポートフォリオだった人にとってはリートなどに分散できます。また現預金を増やしてお金をおろしやすくすると、株式から金利へのシフトもできます(外貨預金だとリスク(価格変動性)が株式などとあまり変わらないので注意しましょう)。
金融資産を取り崩しながら生活資金の一部として活用し、残りは引き続き投資に回していきます。この投資として残す部分は、いわゆる長生きリスクに備えるための資金となります。どの程度の資産を残すかは、ご自身のライフスタイルや価値観に応じて判断する必要がありますが、私であれば、残す資産の多くを分配金重視の投資に切り替えると思います。これは、老後の生活費を補うという目的に適しているためです。また、現時点の投資資産のうち、一定の割合で取り崩していく「定率取り崩し」という考え方も有効です。投資の目的は、広い意味では「老後の生活の足しにすること」で変わりませんが、狭い意味では「老後が来た」ことにより、投資の性格を「積立と成長」から「取り崩しと安定」へとシフトさせる必要があります。
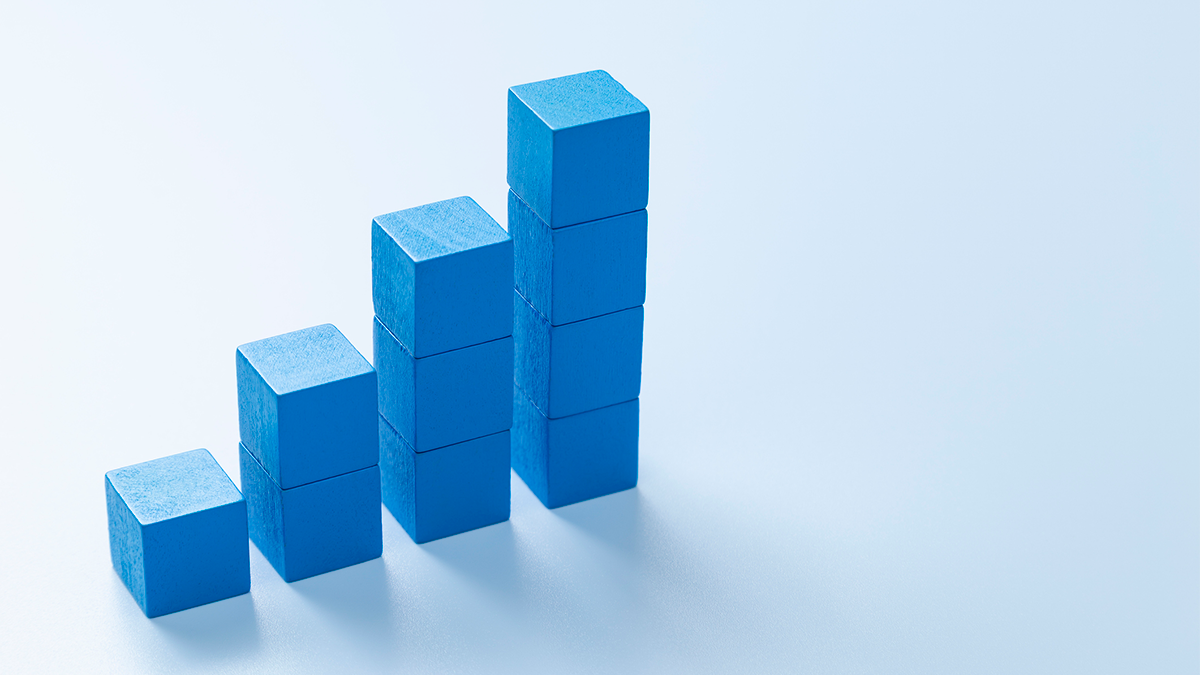
資産形成のゴールは「取り崩し」だ ~神山解説
資産形成のゴールは老後の取り崩しです。長生きリスクに備えて投資を怠ることはなく、しかし生活の潤いを維持していくことが引退後の生活のイメージです。くれぐれも最低限の生活は年金や貯蓄などでクリアし、潤いのある部分を投資成果で楽しむという大枠を忘れないでください。
結局資産形成とはなんでも良いから儲けることではなく、老後の自由になるお金をリスクをとって増やすことだと思います。引退後に収入が減った時にも孫にお小遣いをあげたりちょっと遠くまで旅行したりしたい(この部分が人によるわけですが)ということであれば、その潤いの支出を若い時からの投資で賄いたいということです。長い期間の投資で世界中に分散していれば、元本割れはあまり生じない(人間の努力と工夫で経済が成長すると信じるから)ということが信じられれば、老後のための投資を実行できるでしょう。

特に引退時に退職金をもらい大当たりを狙って唐突に「投資」という投機を始める人が目立ちます。引退時までの積立の投資がない人は、もう取り崩しに入ることを意識した方がいいです。これまでのパフォーマンスや他人に人気の商品を保有するよりも、自分の生活イメージに合わせたポートフォリオを作ることを心がけてください。一部を引き出して潤いのある生活を送り、長生きリスクに備えて高配当株式やリートなどの投資を継続するということを考慮してください。
※以上はくれぐれも神山の感想であっていろんな考え方があるとは思います。投資の参考にどうぞ。
この記事に関連するアモーヴァ・アセットのETF
<世界の株式に分散投資ができるETF>
1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本(愛称:上場MSCI世界株)1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) (愛称:上場MSCIコクサイ株)
<日本の高配当株に投資ができるETF>
399A - 上場インデックスファンド日経平均高配当株50 (愛称:上場日経高配当50)1698 - 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) (愛称:上場高配当)
<Jリートに分散投資ができるETF>
1345 - 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(愛称:上場Jリート)2552 - 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)(愛称:上場Jリート(ミニ))
2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(愛称:上場ESGリート)

<解説者>
神山直樹(かみやま なおき)
チーフ・ストラテジスト。市場環境に応じて、投資の考え方や市場の見方をわかりやすく伝えるレポートや動画、コメントなどをタイムリーに発信している。1985年、日興證券(現SMBC日興証券)入社。日興ヨーロッパ(当時)を経て、1999年に日興アセットマネジメント(現アモーヴァ・アセットマネジメント)で運用技術開発部長・投資戦略部長に就任。以後、大手証券会社・投資銀行でチーフ・ストラテジストなどを歴任。2015年より現職。
【最新のマーケット解説はこちら】
KAMIYAMA Seconds!90秒でマーケットニュースをズバリ解説
●掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また記載内容の正確性を保証するものでもありません。
●当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。
●当資料は、投資者の皆様に「上場インデックスファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
●投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、市場取引価格または基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
●投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。金融商品取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、基準価額と変動要因が異なるため、値動きが一致しない場合があります。
●リスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)などをご覧ください。