本稿は2025年11月5日発行の英語レポート「Future Quality Insights from China」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。
現地での考察
先日、出張で中国に行き、毎年開催されている投資カンファレンスに出席した。中国政府が政策を転換し、一連の景気対策を打ち出してから1年が経つ。筆者は今回が初の中国訪問だったが、カンファレンスには活気があり、投資家たちは慎重ながらも強気な見方を示していた 一方、株式市場の復調は中国の状況を部分的にしか映し出していないことも実感した。
消費者ではなく市場主導の回復
中国政府が景気刺激策へと舵を切った後の株式市場の上昇は、テクノロジー・セクターの堅調なパフォーマンスが原動力となってきた。また、市場はさらなる政策支援の可能性も織り込んでいる。しかし、それ以外の分野では懸念が残る。数十年に一度の大規模な不動産バブル崩壊の真っ只中で、消費者心理は低迷し、貯蓄率は高水準にある。製造業は依然として過剰な生産設備でだぶついており、グローバルに展開する企業はそうした過剰供給分が国内消費者によって徐々に吸収されていくとの見方を明確に示している。深セン、広州、杭州といった一級都市や新一級都市の経済活動は好調と見受けられる。しかし、これらは再び勢いを増している中国テクノロジー・セクターの中核を担う都市群である。下級都市では、需要の低迷や開発された不動産物件の空き家問題など、不動産不況の余波がより鮮明だ。政策当局は金融市場を過度に刺激することを避けながら消費を喚起していくことを目指しており、難しい状況に置かれている。
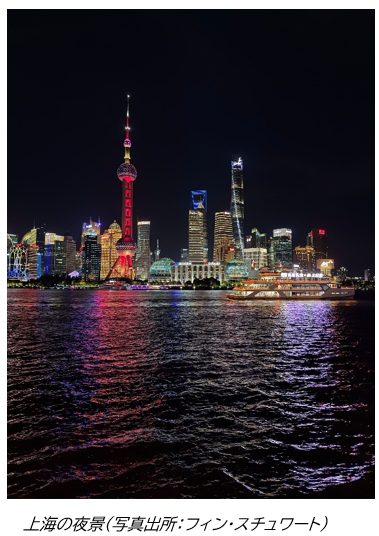
テクノロジー分野の好調が際立つ
投資カンファレンスでは人工知能(AI)関連のテーマが大部分を占め、AIサプライチェーンにおける国内生産能力拡大を推し進める中国の動きや、輸出規制により中国企業が直面している多数の制約などが集中的に議論された。米国との関税合戦が続くなか、中国企業はテクノロジー輸入への依存度を減らすため、国産代替品への移行を迫られてきている。米国に比べると比較対象となる前年水準が低いこともあり、中国による投資額は急増しているが、最高水準の演算性能を持つ半導体にアクセスできないことから、ある程度の水準に抑えられている。中国国内の半導体メーカーの中にはバリュエーションが非常に高水準で推移しているものもあるが、希少性や強い関心を反映したものであり、そうした方向に向かっていることは明らかだ。AI投資を拡大した上場企業の多くは、すでにその成果がみられている。
例えばAlibabaのクラウド事業の売上成長率は、クラウド移行の加速と企業によるAI利用拡大に伴い、一桁台から30%に迫るまでに加速している。Tencentは、ハイエンド半導体へのアクセスが限られているなか、収益性の高いゲーム部門での利活用を優先してきた結果、AIによってゲームデザインの効率や性能を向上させている。このようにAI投資は実際に生産性向上を実現しており、投資がもたらす利益も見通せることから、バブル的な動きというよりも規律ある資本配分であるようにみえる。
フランチャイズの力
企業との面談や現地の生活の観察を通じて特に印象に残ったのは、中国を代表するデジタル・フランチャイズのスケールの大きさだ。Tencent、Alibaba、ByteDanceといったプラットフォームは日常生活に深く浸透しており、それらのエコシステム内で人々がコミュニケーション、決済、ショッピング、エンターテイメントなどに費やす時間も桁外れである。
これらの企業は数十年かけて支配的な地位を築いてきた。現在の課題はリーチ拡大ではなく収益化だ。例えば、Tencent Musicはユーザー拡大からプレミアム化へと重点を移しつつある。平均的な会員の月間支出額は1ドル程度で、この数値を改善していくには顧客が喜んで対価を支払う付加価値の創出が鍵となる。この点において極めて重要な役割を果たすのが強力なフランチャイズであり、当社グローバル株式チームではフューチャー・クオリティの4つの柱のうちの1つに位置付けている。
Trip.comも好例だ。中国政府が消費喚起や国内旅行振興に向けた政策を推進するなか、シームレスな旅行・体験プラットフォームを提供する同社は、そうした取り組みにおいて中心的な役割を果たす存在となっており、サービス支出の回復に伴って恩恵を享受できる有利な位置にある。これらの企業はともに世界的な貿易摩擦の影響をほぼ受けておらず、中国政府が注力する内需拡大政策との足並みも揃っている。
バリュエーション規律は引き続き不可欠
市場の一部、特に半導体サプライチェーン関連銘柄は、ファンダメンタルズ面からは正当化し難いバリュエーション水準で推移しており、割高と見受けられる。一方、インターネット・プラットフォーム大手は、利益率の高いAI事業への移行が続くとすればバリュエーションに割安感がある。いつもながら問題となるのは、規制リスクや地政学的リスクを補うにはどの程度のディスカウントが必要か、である。この点について、足元ではグローバル市場と比較して見直す動きが鮮明になってきている。
数字を超えて
中国に投資する上では、政策と企業の成長がどのように相互に影響し合っているかを理解しておくことが不可欠である。事業拡大には政府の承認が必要な場合が多く、企業は時として政府に目を付けられないように利益を平準化して計上することで知られている。一方、それによって、他国にはみられないある程度の予測可能性ももたらされている。
カンファレンス以外では、中国のインフラとテクノロジーが非常に先進的であることに驚かされた。電車は定時運行され、支払いは完全にデジタル決済化、大都市部は高度に発展している印象を受けた。中国は新興国に分類されているが、多くの都市部の実態とそぐわない。また、自信を持って観光客の誘致拡大に取り組んでいることなどを背景に、訪中旅行客に対する開放性も高まっている感がある。中国によるソフトパワー強化の試みは顕著になってきている。
フューチャー・クオリティ投資プロセスへの示唆
今回の中国出張を通じて、中国には真のフューチャー・クオリティ特性を備え、多くの場合世界の競合他社と比べてバリュエーションが割安な企業が引き続き存在するとの確信が強まった。景気回復はまだら模様かもしれないが、その中には国内事業に注力し、個別要因を追い風とした長期的価値増大の実現が期待される優良企業が存在する。フューチャー・クオリティ企業に投資する当社グローバル株式戦略にとって、これらの銘柄は魅力的な組入候補となっている。
著者の紹介
フィン・スチュワート/グローバル株式ポートフォリオアナリスト
グローバル株式チームをサポートするインターンを経験した後、2022年2月に日興アセットマネジメント(現アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社)に入社し、その後ポートフォリオアナリストとなりました。
セント・アンドリューズ大学にて理論物理学(優等学位)修士取得、CFA資格保有者。

個別銘柄への言及は例示のみを目的としており、当該戦略で運用するポートフォリオでの保有継続を保証するものではなく、また売買を推奨するものでもありません。