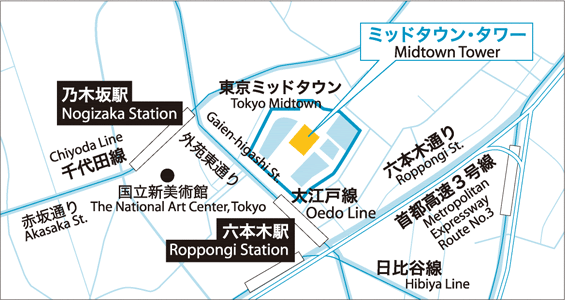2014年、運用益に対して基本的に税金がかからない『NISA(少額投資非課税制度)』が導入されました。そして、2024年からは投資限度額や非課税保有期間が大幅に拡充され、より使いやすくなりました。NISAは、投資家の投資目的や売買機会を変える趣旨ではありませんが、その活用法についてお伝えしたいと思います。
投資成果に税金がかからない、うれしい制度
制度の詳細はNISAを知る:金融庁 (fsa.go.jp)などで詳しく解説されていますので、ここでは省略しますが、NISAを活用することで、年間最大360万円まで投資した場合の運用益(売却益や配当・分配金、以下、リターン)が非課税になるのです。
投資家にとってリターンに対する税金は、投資信託でいう投資先の調査・分析や配分比率の変更といった運用サービスの対価として支払う信託報酬とは異なり、安ければ安いほど良いことは言うまでもありません。
リターンへの課税の有無は、最終的な運用成果に影響します。NISAを活用せずに投資した場合、リターンに対する税率は20.315%(本書執筆時点)です。仮に リターンが3%であれば、税引後のリターンは約2.39%になってしまいます。NISAを活用すれば非課税になるので、リターンの3%がそのまま運用成果になるのです。逆に、税引後のリターンを3%にするには、約3.8%のリターンが必要となります。これは意外に大きいですね。
こう考えると、毎年、投資する際にできるだけNISA口座を使えば、その部分の投資で得たリターンは非課税になります。この意味で、NISAは引退後の「潤いのあるくらし」で消費に使うお金をさらに増やすための“投資するインセンティブ”と位置付けて良いでしょう。
一般・特定口座とNISA口座は、どう使い分けたらいいの?
NISA枠以上の投資をする方は、リターンが大きくなると期待される商品ほど非課税になった際の効果が大きいので、NISA口座を優先的に利用した方が良いでしょう。例えば債券投信よりも株式投信のほうがリスクが大きい分リターンの期待も大きいので、NISA枠は株式投信が優先するでしょう。
投資対象が、長期の積立・分散投資に適した投資信託を対象としたつみたて投資枠と上場株式と一定の条件を満たした投資信託を対象とした成長投資枠は、それぞれ選択できる商品が異なるので、株式、リート、債券など、ご自身の資産全体のバランスが取れるよう、NISA対象商品以外の商品も含めて「組み合わせ」を考えることが必要です。
投資金額が多い人も少ない人もおられますから、答えは一つではありませんが、あまり細かいことにとらわれないでください。まず投資の目的をしっかり持ち、その上で節税をどうするかを考えてみましょう。

- (金融庁ホームページの情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成)