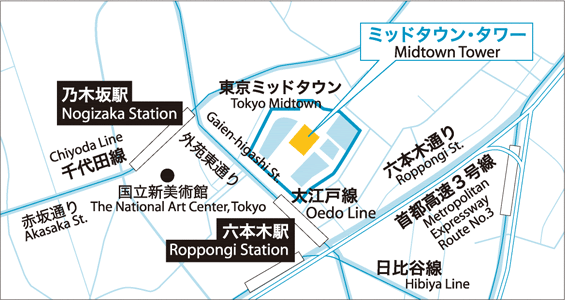ビットコインなどに代表される暗号資産は、送金にかかる時間の短さやコストの低さなどから、画期的な決済ツールとして普及が期待されています。しかし、現状では、その価格変動の大きさなどから、決済ツールとしてよりも、投資資産として話題にあがるケースが目立っています。こうした中、暗号資産の一種である「ステーブルコイン」を巡る動きが国内外で活発化しており、注目を集めています。
価格の安定をめざす暗号資産「ステーブルコイン」
ステーブルコインとは、他の資産と価値を連動させる仕組みなどにより、価格の安定をめざす暗号資産を指します。具体的には、米ドルや日本円といった法定通貨を裏付け資産として1:1の価値で交換できるように設計された「法定通貨担保型」や、他の暗号資産を担保とする「暗号資産担保型」など様々なタイプがあり、特に前者については、価格の安定性が相対的に高いことなどから、ステーブルコインの主流になりつつあります。
ステーブルコインは、迅速な決済や低コストでの取引、24時間365日取引が可能なことなど、暗号資産としての一般的な特徴に加えて、価格の安定性という特有のメリットを有しています【左下表】。そのため、価格変動が大きく決済ツールとして活用しにくいという従来の暗号資産の課題を解消し、今後のグローバル決済の中心的な役割を担う可能性を秘めたツールとして、高い関心が寄せられています。
国内外でステーブルコインを巡る動きが活発化
米国では、2025年7月に、ステーブルコインの包括的な法的枠組みを定めたジーニアス法が成立しました。ステーブルコインに関する規制が明確化されたことにより、暗号資産分野における企業活動の活発化などが期待されます。実際に同国では、大手銀行によるステーブルコイン発行企業との業務提携が発表されたほか、大手小売企業がステーブルコイン発行を検討していると報じられるなど、ステーブルコインを活用したビジネス拡大の兆候が見られます。
日本では、2023年6月の改正資金決済法でステーブルコインに関する法整備がなされていたものの、ビジネス上の取り組みは海外に比べて遅れていました。しかし、足元では、フィンテック関連企業が国内初となる円建てステーブルコイン発行や関連サービスの提供を発表するなど、具体的な取り組みが進展しています。
このほかにも、欧州では、複数の大手金融機関による、ユーロを裏付け資産とするステーブルコイン発行に向けた新会社の立ち上げが発表されました。このように国内外でステーブルコインを巡る動きが活発化する中、主要なステーブルコインの時価総額は急速に拡大しています【右下グラフ】。こうした動きなどに鑑みると、今後、暗号資産分野では、ステーブルコインを中心に関連ビジネスが飛躍的に拡大する可能性もあることから、同分野を世界中で加速する”おカネのデジタル化”を支えるイノベーションの一つとして捉え、注目してみてはいかがでしょうか。
![【図表】[左図]暗号資産の活用による主なメリット、[右図]主要ステーブルコインの時価総額(合計)の推移](/files/market/rakuyomi/images/rakuyomi_vol-2131.jpg)
- 各種報道など信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成
- 暗号資産の一般的な特徴を記載していますが、全てを網羅するものではありません。
- 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。