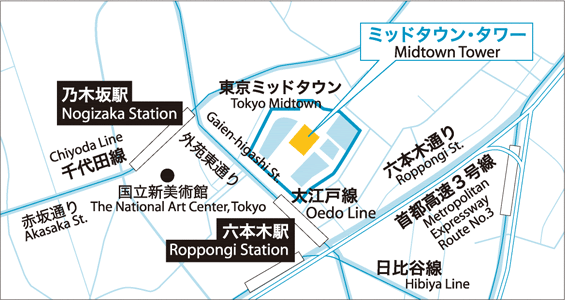足元の米株式市場では、主要な株価指数が最高値を更新するなど、堅調な動きが続いています。この背景には様々な要因が考えられますが、FRB(連邦準備制度理事会)によるこの先の利下げへの期待も、大きな支援材料になっていると見られます。足元の利下げ局面がどの程度続くかは未知数ですが、いずれは利下げの打ち止めが意識されるタイミングが到来し、株式相場の主要テーマから、金融緩和が外れることが想定されます。本稿では、利下げが打ち止めになった後の米国株の動きについて、過去の事例を参考に考えてみます。
利下げの打ち止め後、株価指数は堅調に推移
過去およそ30年間において、米国で継続的に利下げが行なわれた局面は5回あります(足元の利下げ局面は除く)。各利下げ局面における株価指数の動きはまちまちですが、局面③の際にはITバブルの崩壊、局面④の際には世界金融危機などを背景に経済環境が不安定となったことから、株価指数が大きく下落しました【下グラフ】。
一方、利下げ局面が終了した後の株価指数の動きを見ると、局面①~⑤のいずれの場合においても、中長期では上昇トレンドとなったことが読み取れます。株価指数のEPS(一株当たり利益)の推移を見ると、利下げ打ち止め後に一時的に低下することはあったものの、中長期的には拡大傾向となっていました。利下げの効果などから企業収益が回復・拡大するとともに、株価指数もこうした動きを先取り、あるいは反映する形で上昇傾向となったことが伺えます。
小型株とグロース株が高リターンとなる傾向
利下げ打ち止め後の株価指数の動向について、各利下げ局面の終了月(月末)から一定期間の騰落率をサイズやスタイル別に比較すると、小型株とグロース株が特に高いリターンとなったことが確認できます【下表】。利下げの打ち止め後は、相対的な金利水準の低さを背景に、景気や企業業績の回復・拡大期待が拡がることとなり、そうした環境下で選好されやすい小型株や、相対的に成長期待の高いグロース株などが強みを発揮したと考えられます。
このように、株式相場は景気や企業収益の動向を先取り・反映する形で推移する傾向があります。そのため、株式相場の先行きを見通すにあたって、本質的には景気や企業収益の動向が肝要です。つまり、利下げの停止そのものについて心配する必要はなく、以下のデータからは、むしろ、小型株やグロース株が躍進する好機となることが期待されます。
![【図表】[上図]米国の株価指数および同EPS、政策金利の推移、[下図]各利下げ局面終了月(月末)からの各株価指数の騰落率](/files/market/rakuyomi/images/rakuyomi_vol-2134.jpg)
- 当資料に示す各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。
- 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。